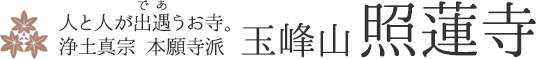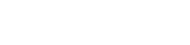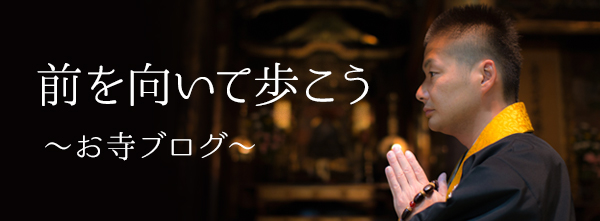2021.11.04
上市の廃村になった村。
開谷。
以前住んでおられた方が、そこからお墓を移設したいとのこと。
お参りに行ってきました。
途中から道幅が狭くなって、向かいから車が来たら大変なことになります。
そして、この山奥に向かいから走ってくる車もなく目的地に到着。
門徒さんが草刈りしてくださったのでお墓までは行けましたが、途中藪に覆われたけもの道を指差して「この向こうにうちの田んぼがあっていつも通ってた」とのこと。
すごいところにおられたんですね。
森の中は下界よりも少し涼しく感じました。
また一つ山の中の墓地が下に降りられる。
私が以前来た時はもっと墓が多かったんですが。
少し寂しい思いをそのご家族と共有しました。

2021.06.21
永代祠堂経(えいたいしどうきょう)の行事が勤まりました。
講師のお話の中で、「微塵」(みじん)という言葉の味わいがとても素敵だと感じました。
微塵は、最小にして最大である。
例年よりも縮小しての開催ではありましたが、こうして無事にお参りができて安堵しました。

2021.06.16
日曜日まで冬の衣を着用する機会があったので、今になって冬衣のクリーニングです。
ワンシーズンで襟や袖にも汗染みが付いてしまうので、しっかり洗濯してもらいます。
ご法事の分だけ衣は各所傷んできますが、少しでも長持ちできるように大切に着させていただいております。
また10月に袖を通すころにはコロナ禍も少し落ち着いていてほしいものです。

2021.05.12
ご門徒さんのお宅にお参りした時のこと。
旦那さんを亡くされて奥さまお一人でお住まいのお宅。
娘さん達がいつもお参りの日に一緒にお参りに来てくださいます。
仏間でお参りした後に、部屋の隅に新しいアイテムがあって気になったので聞いてみました。
「これ、アレクサっていうんですよ」
遠方におられるご家族からちょうどテレビ電話がかかったので、私も会話に交ぜてもらいました。
「お母さんとつながって、離れていても一緒にいるような感じです」
テレビ放送の話題でアレクサを通して、盛り上がったりされているそうです。
とかく便利なものがあると人は楽をしてしまいがちです。
ですが、このご家族は便利なものを使うことで、より深く家族の関わりをもっておられました。
これは本当に画期的です!
年配の方が使い方が分からなくても、離れていても様子がわかって、しかも隣にいるようにコミュニケーションがとれるって素晴らしい!
これは是非とも地域の困ってる人たちに伝えたい。

2021.04.01
今日は私たちの教団の水橋組(みずはしそ)の組会でした。
水橋地区のお西の寺の集まりの総会のようなものです。
僧侶だけではなく門徒議員も加わって、水橋地区の集まりや活動について決算予算も含めて確認してもらいます。
今年度もようやく始まったと実感しました。

2020.11.19
水橋組という水橋地区の浄土真宗本願寺派のお寺の集まりの活動に参加してきました。
今年はコロナ禍で行事が悉く中止です。
毎年楽しみにしている「こども会」も中止となり、子ども達だけでなく私たちスタッフも寂しい思いをしておりました。
そこで、子ども達の寂しい思いを汲んで少しでも笑顔になってもらえるようにと企画しました。
水橋地区の学童施設の子ども達にお菓子のプレゼントです。
学童に通う子ども達がもっともっと来るのが楽しみになりますように!
水橋組の組長さんが誰よりも率先してお菓子などを調達してこられたのに驚きと尊敬を思いました。
お寺はいろんなものをお供えしてもらいます。
仏さまへの「お供え」を、またみんなに「おすそ分け」させていただきます。
人と人との善意の連鎖がずっとずっとつづきますように!


2020.11.16
毎年報恩講にお邪魔した時に、御膳を用意してくださる立山町のお宅にお邪魔しました。
今年はコロナウイルスのこともあり、お土産にお料理を持たせてくださいました。
このお料理、全部奥さんの手作りなんです。
ぎんなんも近所の神社に拾いにいってくださいます。
お野菜は自分のとこの畑で作ったものです。
前日どころか何日も前から下準備をしてくださったお料理の数々。
本当にいつもありがとうございます♪
のっぺ美味しい^_^


2020.10.28
2日間の照蓮寺報恩講の行事。
無事につとまりました。
お参りに来られた方々皆にマスク着用のご協力をいただきました。
御斎の会食の時間がなかったので満足にお話できなかった方もおられたかもしれません。
申し訳ございませんでした。
しかし、久しぶりに皆様のお顔を拝見できてありがたく思いました。
来年はマスクが要らなくなっていればいいなと思います。

2020.02.24
今夜はお通夜。
つい先日新調させていただいた黒衣に初めて袖を通します。
私の声のことを心配して、のどに良いというカリン酒を作って届けてくださった優しい奥様のお通夜。
お通夜のお話は、まずご遺族へのお話だと思っています。
ご往生された方との思い出を懐かしみ、悲しみ、その方と不思議なご縁を結ばせていただいたことに感謝すること。
全てはそこから始まります。
精一杯私もその方とのご縁をかみしめてお話させていただこうと思います。